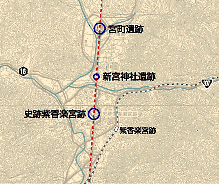
紫香楽宮とその周辺
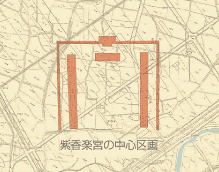
宮町遺跡・遺構配置図
|
【紫香楽宮跡】●信楽町黄瀬 ●信楽高原鉄道紫香楽宮跡駅より徒歩10分 |
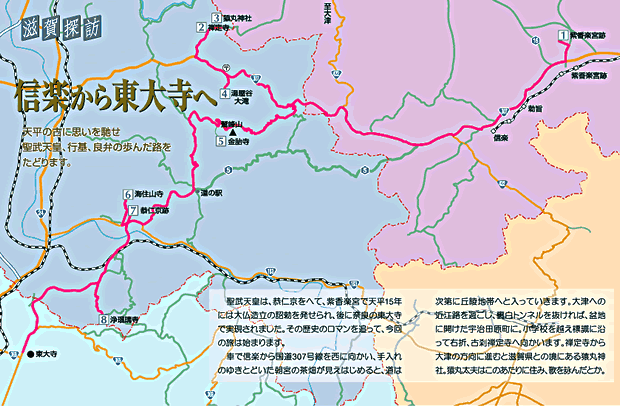
| ①紫香楽宮 (しがらきのみや) | ||
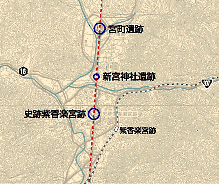 紫香楽宮とその周辺 |
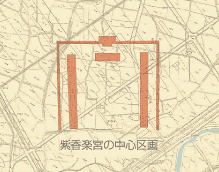 宮町遺跡・遺構配置図 |
|
| かつて「まぼろしの宮」とも呼ばれ、長い間、謎に包まれたままであった聖武天皇(在位724年~49年)の紫香楽宮。つい最近の調査の結果、紫香楽宮とされる宮町遺跡で、その前年に発見された西脇殿に次ぎ、国の政治や儀式をした朝堂院の東脇殿など宮殿の中核施設とみられる3棟の建物跡が発見され大きな話題となりました。その配置が、建物配置の基本となる中軸線上に、大安殿を中心に置き、脇殿を左右に並べる平城京などの古代宮殿と似ており、紫香楽宮が本格的な首都だったことも分かりました。今回の中軸線の確定により、今後様々な建物の存在が明らかになりそうです。 | ||
| 南約1.5キロの史跡紫香楽宮は、天平十六年に大仏の骨組みができたという甲賀寺跡ともいわれ、次々と謎が解き明かされて歴史の舞台がようやくその全貌をあらわそうとしています。 | ||
|
||
| ②禅定寺(ぜんじょうじ) |  |
| 奈良東大寺の別当職であった平崇上人草創と伝えられ、本尊は十一面観音。茅葺き屋根の本堂には山寺らしい趣が。この高台から見おろす宇治田原の景色の美しいこと。 | |
③猿丸神社(さるまるじんじゃ) |
|
「奥山に紅葉ふみわけ鳴く鹿の声聞くときぞ秋はかなしき」の名歌で知られる猿丸太夫を奉り、毎月13日は「猿丸市」が開かれ人でにぎわいます。
|
|
| 猿丸神社を後にして、再び国道307号を信楽方面に戻り、郵便局前を右に折れ、天平時代温泉場があったという湯屋谷に向かいます。湯屋谷地区は日本緑茶の祖、永谷宋円ゆかりの地。集落を越え細い道を奥へ進んでいくと、湯屋の大滝が現れます。深い谷から清らに流れ落ちる滝を見ていると、身も心も引き締まるような気がします。 | |
| ④湯屋谷の大滝(ゆやだにのおおたき) | |
| 霊峰鷲峰山の深い谷から流れ出る沢山の滝の一つで、水の神が奉られています。 |  |
|
|
| 古い修験道の霊山鷲峰山へは、昔の行者達は、溝のような細い道を登ったのでしょうが、今回は車なので一旦国道307号線にもどり、東へ、283号線方向に向かって進みます。283号線には途中で別れを告げ、道の両サイドに美しい杉木立が続く林道を何度もカーブを曲がりながら登っていきます。金胎寺参道の立て札を見つけたら、ここからは徒歩で7分位。山頂には、金胎寺の多宝塔が深い静けさの中佇んでいます。周辺は芝生の広場もあり、宇治田原の町を一望に、お弁当を食べるのにはベストロケーション。 | |
| ⑤金胎寺(こんたいじ) | |
| 役行者が開祖と伝わっています。多宝塔は鎌倉時代の建築で、重厚な姿に魅了されます。 |  |
|
|
| 鷲峰山からは、地福谷方向へ降りていき、62号線を和束町方向へ行くと「道の駅茶処和束」が角にある大きな交差点に出ます。道の駅では、麺類なども食べられるレストランが併設されてるので、一服するのもいいかも。この交差点を右折、5号線に入ります。その先、この道は伊賀街道国道163号線に合流、すぐの交差点に海住山寺の大きな案内塔が立っています。白洲正子さんが著書「十一面観音」のなかで、「最近はお寺(海住山寺)まで自動車道がついたと聞き、安心していたら修理中で、又歩く始末となった」という自動車道を上がっていくと、加茂町を一望できるの山の上に海住山寺はあります。 | |
| ⑥海住山寺(かいじゅうせんじ) | |
| ここも十一面観音を本尊とし、天平7年(735年)に聖武天皇の勅願により、良弁僧正が開創。山門左手には美しい五重塔が。 |  |
|
|
| 山道を下っていくと、伊賀街道に出るまでに、恭仁京跡はあります。現在は大極殿跡や国分寺跡を記した石碑が立ち、春は桜、夏にはホタル、秋にはコスモスが咲き、憩いの場所になっています。一路、加茂駅を目指して、恭仁大橋を渡ります。この下を流れる木津川は、昔は、甲賀、伊賀から切り出された木材の運搬や近江からの物資を運ぶのに利用されていたそうです。きっと大仏建立のための物資もここを通っていったに違いないと想像を巡らすのも楽しいもの。 | |
| ⑦恭仁京大極殿跡・山城国分寺跡(くにきょうだいごくでんあと・やましろこくぶんじあと) | |
| 恭仁京は、日本史上一番短命の都(740~744年)と知られています。廃都後は山城国分寺が造営されて繁栄しました。 |  |
|
|
| 浄瑠璃寺へは、JR加茂駅を過ごし、踏切を渡り現代風の建物が立ち並ぶ南加茂台の住宅地を通り抜けていきます。少し行くとさっきとはうって変わって、鄙びた畑の風景が広がり郷愁を誘います。坂を登っていくとその先にようやく浄瑠璃寺が姿を現します。浄瑠璃寺からは、来るときは余裕がなく気がつかなかった眺望を楽しみながら、高田の交差点までもどり、44号線を使って梅谷口まで。ここまでくれば、もう奈良県との境。最終地の東大寺へは、あと一息です。 | |
|